
想いと豊かさを未来へ繋ぐ案内人
相続対策コンサルタント
堀亜砂子です!
「認知症対策には家族信託が良いらしい。」
そんな話を耳にしたことはありませんか?
なんとなく聞いたことはあるけれど、
具体的にはよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
家族信託とは一言で言うと
「家族のために家族が財産を管理する仕組み」です。
例えば認知症になってしまったら、
本人が財産の管理や契約をすることが難しくなる可能性があります。
そんなとき、事前に信頼できる家族に財産の管理を託しておくことで
財産の凍結を防ぎ、本人の生活を守ることができるのです。
家族信託とは?
家族信託とは、財産を持つ者(委託者)が、財産の管理・運用を信頼できる家族(受託者)に託し、
その収益を委託者自身や指定した受益者が受け取る仕組みです。
正式には「民事信託」とも呼ばれますが、信託契約によって財産の名義を受託者に移転させ
受託者が契約の内容に基づき財産の管理・処分を行います。
この仕組みによって、認知症や判断能力の低下に備えて財産の管理・運用をスムーズに行えるようにしつつ
遺言や贈与では対応しきれない柔軟な財産承継も可能となります。
一般的な信託の仕組みには次の3者が登場します。
【委託者】 信託財産のもともとの所有者。信託契約を設定する人。
【受託者】委託者から財産の管理・運用を任される人。信託契約に基づき財産の管理義務を負う。
【受益者】 信託財産からの収益を受け取る権利を持つ人。
例えば、Aさん(委託者)が自身の所有するアパートを息子のBさん(受託者)に託し
Aさん自身が受益者となる家族信託を設定します。
信託設定後、アパートの法律上の所有者はBさんになりますが、
実質的な収益は引き続き受益者であるAさんが受け取ります。
この仕組みにより、Aさんが認知症などで意思判断能力を失った場合でも、
Bさんが契約内容に基づきアパートの管理・運用を続けることができるため、収益が途絶える心配がありません。
信託の特徴とメリット
信託には以下のような特徴やメリットがあります。
- 信託財産の分別管理
- 信託財産は委託者や受託者の財産とは分けて管理されます。
- 受託者が破産しても、信託財産は差し押さえの対象にはなりません。
- 信託契約の柔軟性
- 遺言とは異なり、財産の分配や管理方法を柔軟に設計できます。
- 例えば、「受益者が死亡した後の財産の行方」もあらかじめ決めておくことができます。
活用例:認知症対策としての家族信託
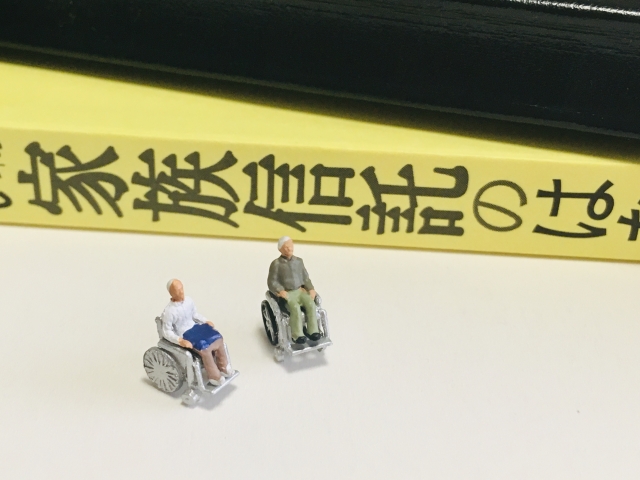
(事例1)アパート経営と認知症対策
築35年のアパートを所有している80歳のAさんは、建物の老朽化が進んできたことをきっかけに、
今後の管理体制を見直すことにしました。
「将来的に自分が賃貸管理を続けられなくなったらどうしよう…」という不安を抱えたAさんは、
認知症発症のリスクにも備えるため、息子のBさんを受託者として信託契約を締結しました。
- 委託者:Aさん
- 受託者:長男のBさん
- 受益者:Aさん
- 信託財産:賃貸アパート
信託契約の締結により、アパートの所有権は法務局への登記を経てBさんに移転しますが、
Aさんは受益者として引き続き賃料を受け取ります。
そしてAさんが認知症になった場合には、Bさんが契約内容に基づき、アパートの賃貸管理や修繕を行うことが可能です。
さらに、Aさんの死亡後は、残余財産としてアパートやその収益はBさんが受け取ることになります。
(事例2)預貯金の管理と生活費の確保
最近、物忘れが増えてきたと感じている75歳のCさんが、将来的な認知症発症のリスクを考えて信託契約を締結しました。
- 委託者:Cさん
- 受託者:長女のDさん
- 受益者:Cさん
- 信託財産:預貯金1,000万円
信託契約に基づき、DさんはCさんの生活費や医療費の支払いを行うことができます。
Cさんが認知症になった場合でも、Dさんが信託契約の内容に基づき、必要な支払いを継続して行うことができます。
(事例3)自宅の維持管理と生活支援
68歳のEさんは持ち家に住んでいますが、最近自身の健康状態に不安を感じ始めました。
そこでEさんは、自宅の維持管理と生活費の確保のため、息子のFさんと信託契約を締結しました。
- 委託者:Eさん
- 受託者:息子のFさん
- 受益者:Eさん
- 信託財産:自宅および預貯金500万円
契約内容には「自宅の修繕費用を優先的に支出する」旨が定められており、FさんはEさんが病気で入院したり
認知症で判断能力を失った場合でも、自宅の維持管理を適切に行うことができます。
これらの事例からもわかるように、家族信託は単なる財産管理だけでなく、
認知症対策としても非常に有効な手段のひとつといえます。
事前に信託契約を設定しておくことで、認知症による財産凍結を防ぎつつ、
資産の管理・運用をスムーズに行うことが可能になるのです。
ただし、家族信託の仕組みだけでは、生活面のサポートや医療同意といった「身上監護」には対応できません。
これらについては成年後見制度や親族の見守りを併用することで、より包括的な支援体制が整います。
税務上のポイント
信託には税務上の特別なルールが存在します。
【所得税の取扱い】
受益者が信託財産の所有者とみなされ、信託財産から得た収益はその受益者の所得として課税されます。
【贈与税の取扱い】
委託者以外の者が無償で受益者となる場合や、信託期間中に受益者が変更された場合、その受益権の移転が贈与とみなされることがあります。
【相続税の取扱い】
受益者の死亡により受益権が承継される場合、その承継が遺贈とみなされ相続税の対象となります。また、受益者の死亡によって信託が終了し、残余財産があらかじめ定めた者に帰属する際にも、その財産の移転が相続税の課税対象となります。
税務上の手続きと留意点
1.税務署への提出書類
(1)信託の計算書
受託者は、信託財産に係る収益の額の合計額が3万円 (計算期間が1年未満の場合は1万5千円)以下であるなど 一定の場合を除き、毎年1月31日までに前年の信託財産の状況等を記載した 「信託の計算書」及びその合計表を提出しなければなりません。 「信託の計算書」(国税庁ウェブサイトより)
(2)不動産所得に関する明細書
受益者は、信託から生じる不動産所得がある場合には、 信託ごとに作成した収支内訳書(不動産所得用)または 損益計算書(青色申告決算書 不動産所得用)を確定申告書に添付して 提出しなければなりません。
たとえば、賃貸物件の一部についてのみ家族信託を設定した場合は、 信託していない物件とは別にこれらの書類を作成する必要があります。
「税務上のポイント」に記載のとおり、税務上は受益者が財産の所有者と みなされるため、上記の(事例1)でアパートの賃料などは信託設定後も受益者であるAさんの 収入として不動産所得の申告を引き続き行うことになりますが 、
このように信託財産については区分して明細を作成しなければならなくなります。
(3)信託に関する受益者別(委託者別)調書
受託者は、信託について税務上贈与や遺贈と認識される事由が生じた場合、 信託財産の価額が相続税評価額で50万円超のときは、税務署長に対し 翌月末日までに「信託に関する受益者別(委託者別)調書」及びその合計表を 提出しなければなりません。(相続税法59条③、相続税法施行規則30条) 信託に関する受益者別(委託者別)調書(同合計表)
2.税務上の留意点
(1) 不動産所得の赤字は損益通算不可(損失はなかったものとみなされる)
信託財産から生じた損失は、原則として経費(費用)になりますが、その損失が不動産所得に関するものである場合、 2006年(平成18年)以後は、不動産所得の計算上なかったものと みなされ、他の所得との損益通算ができないこととされました。 (租税特別措置法41の4の2①)
(2) 空き家特例の適用除外
「空き家特例」とは、被相続人が居住していた家屋について、相続発生後に一定の要件を満たして売却した場合に適用される特例(3000万円の特別控除)ですが、信託財産となった不動産については適用を受けることができないこととされているため、信託の設定にあたっては慎重な検討が必要です。
文書回答事例(令和4年12月20日)「信託契約における残余財産の帰属権利者として取得した土地等の譲渡に係る租税特別措置法第35条第3項に規定する被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用可否について」
(国税庁ウェブサイトより)
(3) 贈与があったものとみなされる場合
「税務上のポイント」に記載のとおり 税務上は受益者が信託財産の所有者とみなされることから、委託者以外の者が対価を払わずに受益者となる信託を設定した場合、その受益権の取得は贈与とみなされます。
また、 信託期間中に受益者が変更されたり、信託終了時に受益者以外の者が 残余財産の帰属権利者として給付を受ける場合にも これらの者に対して贈与があったものとみなされるので注意が必要です。
まとめ

家族信託は、認知症対策や財産管理の手段として非常に有効な仕組みです。
しかし、その契約内容や税務上の取扱いには専門的な知識が求められます。
信託契約を安易に設計してしまうと、法的に無効となるリスクがあるのはもちろんのこと、
税務面の検討を怠ったことで予期せぬ課税が発生するケースも少なくありません。
こうしたリスクを避けるためにも、信託契約の設計時には法務・税務の専門家と連携し、
慎重に検討を進めることが重要です。
信託の活用を検討する際には、早めの段階で専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
「突然の別れ」は、誰にとっても他人事ではありません。
だからこそ、“その時”が来る前に、できる準備を。
あなたやご家族の大切な想いを、
静かに、でも確かに未来へつなげるために─
相続や生前対策に関するご相談はお気軽にどうぞ!
イベントやお得な情報をメルマガやLINE公式からご案内しています!
★「想いと豊かさを未来へ繫ぐメルマガ」
ご登録で2つのプレゼント🎁
その1「想いを繫ぐ 相続診断チェックシート」
その2「相続トラブルを防ぐ3つのステップ」
★LINE公式
ご登録で動画プレゼント🎁
\知らないとヤバい!?/
「相続対策が今すぐ!必要な理由」

★はじめの一歩にぜひどうぞ【note記事】
\生前対策 “はじめの一歩” /
専門家に相談する前に 家族で相続を考える「3つの質問」
※画像をクリック!

